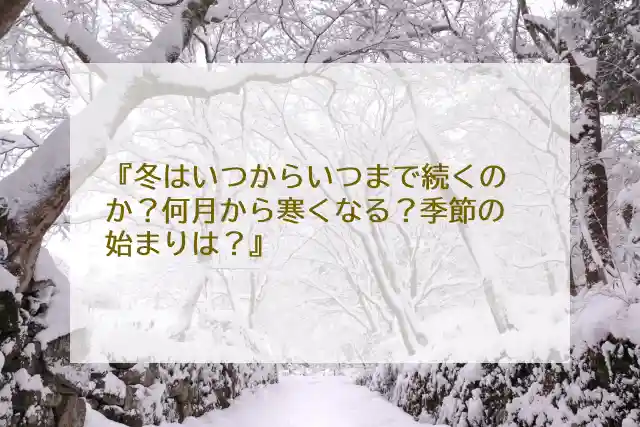秋の涼しい日々が終わると、やがて厳しい冬が訪れます。
この季節になると、雪が降ることもあり、服装もより暖かいものに変わります。
そんな中で、「冬って具体的にいつ始まるんだろう?」と思うことがあります。
多くの人は11月や12月頃から冬らしく感じるかもしれませんが、正確な時期を尋ねられると答えるのが難しいですよね。
この記事では、冬がいつ始まり、いつ終わるのかを掘り下げています。
気象庁や旧暦、天文学など様々な観点から冬の期間を検討してみました。
是非、最後までご一読ください。
冬の期間はいつからいつまで?
その質問には、実は一つの答えではなく、複数の答えが存在します。
以下、異なる分野からの冬の定義を探ってみましょう。
気象庁による冬の定義
気象庁では、冬は12月から2月とされています。
この時期、日本海側では雪が多く降りますし、一部地域では雪が3メートル以上積もることも。
一方で、太平洋側では晴れる日が増えます。
気温は北海道では氷点下になることもあれば、沖縄では15℃以上になる日もあります。
日本は地域によって冬の気温が大きく異なるんですね。
四半期で見た冬
四半期は、会計年度や学校年度などで使用される期間の区切り方です。
これに基づくと、冬は1月から3月となります。
学校ではこの期間が学年の最後の学期であり、卒業式など重要な行事が行われる時期です。
1月は雪が降る季節であり、3月末には桜が美しく咲き始める時期です。
各分野で見ると、冬の定義は異なりますが、気象庁の定義である「12月から2月まで」が一般的な認識と言えるでしょう。
天文学における冬
天文学的には、冬は冬至から春分までとされています。
例えば2023年の冬至は12月22日の金曜日、2024年の春分は3月20日の水曜日です。
これに基づくと、2023年の冬は12月22日の金曜日から3月20日の水曜日までと定義されます。
面白いことに、インターネットで「冬はいつからいつまで?」と検索すると、この天文学的な定義がよく出てくるんですよ。
旧暦に基づく冬
旧暦では、冬の定義には二つのアプローチがあります。
まず、「月切り」という方法では、冬は旧暦の十月から十二月までとされています。
もう一つの「節切り」では、立冬から立春の前日までを冬とします。
旧暦に基づく季節の捉え方は、現代の暦とは異なる特徴を持っています。
旧暦における「月切り」での冬
旧暦の「月切り」では、冬は十月から十二月までの期間を指します。
これを現代のカレンダーに当てはめると、2023年の場合、旧暦の十月は11月13日から始まり、十二月は2024年の2月9日に終わります。
したがって、旧暦の月切りに基づく2023年の冬は、11月13日から翌年の2月9日までとなります。
「節切り」による冬
「節切り」とは二十四節気を基にした季節の区分けです。
1年を春夏秋冬の四季に分け、各季節をさらに6つの節気で細分化します。
この考えに基づくと、冬は以下のようになります。
- 立冬(りっとう) :11月7日頃
- 小雪(しょうせつ):11月22日頃
- 大雪(たいせつ) :12月7日頃
- 冬至(とうじ) :12月21日頃
- 小寒(しょうかん):1月5日頃
- 大寒(だいかん) :1月21日頃
冬の始まりを示す立冬は11月7日頃で、春の始まりである立春は2月4日頃です。
これにより、節切りに基づく冬の期間は11月7日から2月3日までと定義されます。
冬のはじまり・最寒月・降雪について
冬のはじまりは何月?
冬というと寒い季節を思い浮かべますが、「実際にいつから寒さを感じ始めるのだろう?」と疑問に思うことがあります。
人が感じる寒さの温度は以下のように分類されます。
- 肌寒い :15℃~22℃
- 寒いと感じる:8℃~14℃
ただし、これは単に気温だけではなく、それがどれだけ相対的な温度変化であるかも関係します。
たとえば、夏の暑い日から15度の部屋に入ると寒く感じますが、冬の寒い日から同じ温度の部屋に入ると暖かく感じます。
そのため、「何度になったら寒い」と一言で言うのは難しいです。
東京都の12月の平均最高気温と最低気温では、12月1日には最高気温が既に14℃と寒い範囲に入り、その後さらに下がっていきます。
これを考慮すると、12月には既に冬の寒さが始まっていると言えます。
一年で最も寒い時期
通常、一年の中で最も寒い時期は1月下旬とされています。
2023年の東京の1月の気温は、1月25日の東京では最高気温が3.7℃に達し、非常に寒い日となっています。
また、1月23日と27日には最高気温が7℃以下となる日もあります。
それらを考慮すると、一年の中で最も寒いのは1月下旬であることが分かります。
一方で、12月は基本的に1月ほど気温が下がることは少なく、2月に入ると寒い日がありますが、下旬になると徐々に気温が上昇する傾向にありるのです。
雪の季節の到来
冬の代表的な現象と言えば、雪ですね。
日本の各地では、雪がいつから降り始め、いつまで続くのでしょうか。いくつかの地域の初雪と最終雪の日を見てみましょう。
- 札幌… 10月28日~4月19日
- 仙台… 11月24日~4月7日
- 前橋… 12月15日~3月22日
- 東京… 1月3日~3月11日
- 名古屋…12月20日~3月7日
- 京都… 12月15日~3月20日
- 大阪… 12月22日~3月11日
- 鳥取… 12月5日~3月25日
- 福岡… 12月15日~3月5日
- 那覇… めったに雪は降らない
特に興味深いのは、東京より南に位置する福岡の初雪が早い点です。
これは福岡が日本海側に面しているためで、日本海側は太平洋側に比べて寒さが厳しく、雪が積もりやすい傾向にあるからです。
このような地理的な特徴を知っておくと面白いですね。
まとめ
この記事では、「冬はいつから始まるのか」という疑問について解説しました。
冬の始まりは以下のように異なる定義があります。
- 気象庁の秋…12月~2月
- 四半期の秋…1月~3月
- 天文学での秋…冬至(12月22日)~春分(3月21日)
- 旧暦の秋…10月~12月(月切り)、立冬~立春の前日まで(節切り)
これらの定義によると、12月から2月までが一般的に寒いとされる冬の期間と定義して問題ないでしょう。
ただし、日本では地域によって冬の気候が大きく異なります。
北海道では11月から4月にかけて雪が降り続き、氷点下の気温になることが多いですが、沖縄では雪はほとんど降らず、2月でも比較的温暖です。
そういった各地の条件も考慮する必要があるかもしれませんが、
冬はいつからいつまで?
の答えは
12月から2月まで
となります。