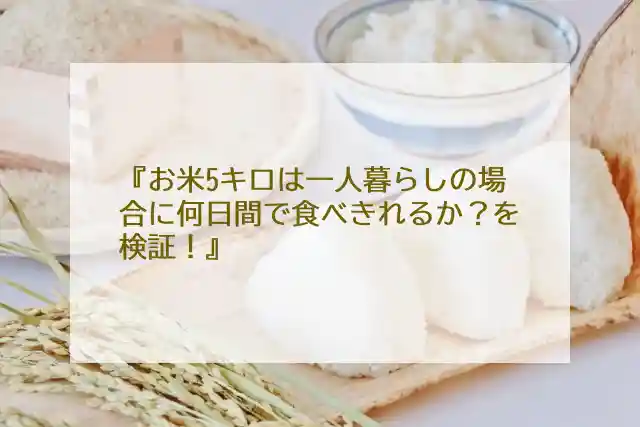一人暮らしの自炊者が5キロのお米をどれくらいの期間で使い切るか、という疑問を解説します。
5キロのお米は大体33合分であり、もし1日に2食ご飯を食べる場合、約40日で食べ尽くすことになります。
さらに、このお米がお茶碗何杯分になるのか、それに基づいて計算して、1杯あたりのコストも考えてみましょう。
5キロのお米は何合に相当するのか?
そしてそれがお茶碗何杯分か、さらには炊いたご飯の重さについて解説します。
まず、お米1合の平均重量は約150グラムです。
したがって、5キロ(5000グラム)のお米を1合の150グラムで割ると約33合と計算できます。
ただし、お米の種類や含まれる水分によって重さは若干異なることがあります。
お茶碗一杯のご飯は大体0.5合ですので、1合だとお茶碗2杯分に相当します。
では、お米1合を炊くとどれだけのご飯ができるかというと、以下の換算式を使用します。
お米の重量(g)×2.2~2.3=炊いたごはんの重量(g)
お米150Gg(1合)×2.2=330g(炊いたご飯)
この式によると、150グラムのお米を炊くと約330グラムのご飯ができます。
また、お米1合の体積については、180ccが一般的です。
日本では180ccと200ccの計量カップがありますが、180ccの計量カップは特にお米1合を測るために作られています。
5キロのお米は何日分(一人暮らし)?
5キロのお米が一人暮らしの場合、どれくらいの期間で使い切れるかを考えてみましょう。
まず、一般的なご飯の量からスタートします。
- 軽めのお茶碗一杯は約100グラム(168キロカロリー)
- 普通盛りのお茶碗は約140グラム(235キロカロリー)
- 大盛りのお茶碗は約240グラム(403キロカロリー)
普通盛りの量を基準にすると、1合のお米はお茶碗で約2.4杯分に相当します。
したがって、5キロのお米はおおよそ33合ですから、33合×2.4杯で約79杯分のご飯ができます。
一人暮らしで毎日朝昼晩に1杯ずつ食べるとすると、79杯を3杯で割って、約26日間で5キロのお米を使い切ることになります。
また、4人家族が同じように朝昼晩に1杯ずつ食べる場合、1日で12杯消費します。
その場合、約6.5日で5キロのお米がなくなる計算になります。
ただし、実際のご飯の量は日によって異なるため、これらはあくまで目安として考えてください。
茶碗一杯当たりの値段
ご飯茶碗一杯当たりのお米の値段を計算してみましょう。
お米の価格は品種や店によって異なりますが、例として近くのスーパーで5キロ(33合)が2000円で売られているとします。
この価格を元に計算すると、
お米1合の価格は
2000円(お米5㎏)÷33合=約61円
となります。
1合はお茶碗で約2.4杯分ですから、61円÷2.4杯でお茶碗1杯当たりの値段は約25円になります。
それでは10キロのお米を購入した場合はどうでしょうか?例えば10キロが3500円だとしたら、
お米1合の価格は
3500円(お米10㎏)÷66合=約53円
この場合、53円÷2.4杯でお茶碗1杯分の値段は約22円となります。
この計算から、5キロを購入するよりも10キロを購入する方が経済的であることがわかります。
開封後のお米の適切な保存期間と保存方法
開封後のお米の適切な保存期間と保存方法について考えてみましょう。
お米は開封後どれくらいで食べきるべきでしょうか?
一般的に、白米は常温で保存した場合、1ヶ月以内に食べることが推奨されます。
季節によって保存期間は異なり、冬ならば2~3ヶ月、夏や梅雨の時期には2~3週間が適しています。
精米されたお米は酸化が進むため、美味しく食べるためには、1ヶ月以内に消費できる量を購入するのが良いです。
また、お米を美味しく保つためには保存場所の条件も重要です。
主な注意点は「温度」「湿度」「空気」で、以下のような場所が適しています。
- 直射日光の当たらない暗い場所
- 温度変化が少ない場所
- 湿度が低い場所
- 他の食品のにおいが移りにくい場所
例えば、台所のガスコンロ下や日光が直接当たる場所は温度が上がりやすく、虫が発生しやすいです。
また、流し台下など湿度が高い場所はカビの発生リスクがあります。
最適な保存場所は「冷蔵庫」です。
お米を密閉できる容器やジップ付きの保存袋に入れて、冷蔵庫の野菜室での保存がおすすめです。
冷蔵庫であれば、おおよそ3ヶ月が保存の目安となります。
また、冷蔵庫用の米びつも市販されており、これを使うと場所を取らず便利です。
炊いたご飯の保存方法
炊いたご飯の保存方法として、炊飯器での保温、常温保存、冷蔵庫、冷凍庫の4つの方法がありますが、どの方法が一番良いでしょうか。
最も美味しく保存できるのは「冷凍」です。
お米に含まれるでんぷんが水分を失うと、「老化」という現象が起こり、食感が硬くなり風味が落ちます。
この老化を防ぐためには、水分を含んだ状態で冷凍するのが効果的です。
1.炊けたばかりの熱いうちにラップで包む
炊けたご飯は、保温による劣化を避けるために早めにラップで包みます。
熱いうちに包むことでラップに水滴がつくのですが、この水分が重要です。
平らに包むと冷凍・解凍がスムーズに行えます。
2.すぐに冷凍する
ラップで包んだご飯の粗熱が取れたら、すぐに冷凍庫に入れます。
アルミトレーやアルミホイルを使うと、より早く冷凍できます。
3.解凍は電子レンジで
自然解凍や冷蔵庫で解凍すると時間がかかり、ご飯のでんぷんが固くなりがちです。
電子レンジで加熱することで、ふっくらと柔らかいご飯を再現できます。
適してない保存方法
炊飯器や冷蔵庫でのご飯の保存方法については注意が必要です。
炊飯器で長時間保温しておくと、ご飯が乾燥してしまったり、色が変わったり、変なにおいがついてしまう可能性があります。
保温は最長で5~6時間以内が望ましいです。
また、冷蔵庫での保存も推奨されません。
なぜなら、冷蔵庫内の温度がでんぷんの劣化につながりやすく、ご飯のパサつきや味の低下の原因になるからです。
まとめ
一人暮らしの場合、約26日で5キロのお米を使い切ることができます。
ご飯茶碗一杯あたりのコストも約25円と、外食に比べてコストを抑えることが可能です。
美味しくお米を楽しむためには、短期間で食べきれる量を購入し、適切な保存場所と方法を選ぶことが大切です。